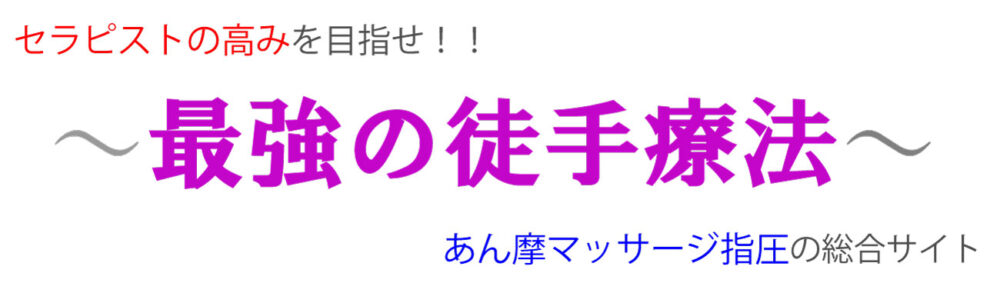この記事では、柔道整復師について解説しています。
「柔道整復師学とマッサージ師が同時に学べる学校」も存在するので以下を知りたい人は多のでは。
- 柔道整復師ってどんな資格?
- マッサージ師と何が違う?
これらの疑問に対して、個人的な見解を述べていきたいと思います。
目次
柔道整復師とは?
柔道整復師とは以下を指します。
でもって、柔道整復師の施術とは「整復法」「固定法」「後療法」の3つを言います。
整復法
整復法は「骨折や脱臼を元に戻すための操作技術」のこと(この操作をした後に固定法をほどこす)。
固定法
固定法は「骨折・脱臼・捻挫などを(必要に応じて整復した後に)三角巾・包帯・副木などで固定して治癒を促す方法」を指す。
後療法
後療法は「損傷した組織を回復させる治療法」を指す。
後療法は「物理療法」「運動療法」「手技療法」の3つに分けられる。
柔道整復師は過去の産物
柔道整復師に関して、なんとなくピンときましたか?
ただし、柔道整復師が上記の「整復法」と「固定法」を臨床で使う頻度は極端に減ってきています。
っというのも骨折・脱臼・(中度、重度な)捻挫の場合は、多くの人かま整形外科を受診するようになっているからです。
皆さんは腕を骨折した際、接骨院へ行きますか?病院へ行きますか?
昔は「接骨院へ行く」という人も多かった。
その理由は以下の通り。
ですが今は、整形外科病院が地域に充実する一方で、柔道整復師学校の乱立により玉石混合な接骨院で溢れかえっています。
そのため「経験が乏しく授業以外に整復法・固定法をほどこしたことは一度もない柔道整復師」も増えている。。
そうなると、「接骨院へ駆け込んだは良いけど上手く治療してもらえなかった」ということも増えてきます。
すると尚更「骨折・脱臼・(中度・重度な)捻挫は整形外科医で治療してもらう」といった流れが強化されしまうという訳です。
この様に考えていくと「整復法」と「固定法」は、学んでも臨床で役立てる機会は少ない学問となっている気がします。
もちろん「私は整復法・固定法を使っている」とい柔道整復師が少なからず存在していることは知っています。
また、スポーツ分野などでの応急処置的な役割も担えます。
ただし、乱立した学校から年々排出されている多くの柔道整復師に対する「一般論」は、このブログで記載しているとおりです。
繰り返しになりますが、(病院が少なかった昔はいざ知れず)現在は柔道整復師の多くの部分を整形外科病院が担う事が可能となっています。
昔のように整形外科病院の受け皿にはなり得ないという訳です。
それでは、柔道整復師の施術の一つ「後療法」についてはどうでしょう。
後療法も柔道整復師に特化した治療法ではない
ここまでの話として、柔道整復師の施術(整復法、固定法、後療法)のうち、「整復法・固定法は時代とともにニーズが激減している」という話をしました。
では後療法はどうでしょう?
柔道整復師の後療法は以下であると前述しました。
ただし物理療法・運動療法は、整形外科病院のリハビリとして代替え可能なんですよね。
物理療法に関して
リハビリ室・物理療法室へ行けば、物理療法機器も(個人でお金を払って揃えている接骨院と比べて)充実している傾向にあります。
運動療法に関して
運動療法に関しては理学療法士の方が専門的です。
また接骨院では、どちらかというと徒手療法がメインな傾向が強く、運動療法を実施していたとしても「徒手療法のおまけ」あるいは「自主トレとして指導」くらいで終わることの方が多いです。
確かに地域によっては、「整形外科病院が少なく、接骨院が重要な役割を担っているケース」も有ります(例えば、離れ島なんかは、凄くありがたがられ繁盛していると聞きます)。
ですが、大多数のケース(一定以上の人口密度のある地域の接骨院)においては、柔道整復師は役割を終えているというのが実情です。
手技療法について
後療法の「物理療法」「運動療法」について前述したとおりですが、「手技療法」はどうでしょう。
実は手技療法に関しても「柔道整復師ならではの特徴」ではないんですよね。
手技療法は「あん摩マッサージ指圧師」「整体師」「理学療法士」など多くの資格に共通している技術です。
そして、上記資格者が様々な手技療法を生み出しています。
一方で、柔道整復師が生み出した「手技療法」はピンときません。
海外には「柔道整復師に代わる資格」が無いわけですから、手技療法を得意とする柔道整復師の内情をみても以下などで、柔道整復師オリジナルなものはお目にかかったことはありません。
- カイロプラクティック・オステオパシー(日本では民間療法に該当)
- 操体法などを含めた多くの整体手技
- AKA(=関節運動学的アプローチ。海外の医師・理学療法士が主に発展させてきた。関節モビライゼーション含む。いずれにしても柔道整復師オリジナルではない)
- AKA博田法(日本の医師が考案した。以前は柔道整復師も学ばせていたが、現在は医師以外にPT・OTのみ学ぶことが出来る)
- 軟部組織に対するアプローチ(主にあん摩マッサージ指圧師が発展させてきた)
要するに、多職種の手技療法をパクって使ってるだけなんですよね。
まぁ、そもそもが「急性外傷における整復法・固定法に強みのある資格」というのが出発点なため、手技療法が発展していれば、それはそれで本来の役割とは違った方向へ向いているということになりますが。
柔道整復師の固定法・整復法・後療法まとめ
繰り返しになりますが、前述した「固定法」「整復法」は、マッサージ師、整体師、療法士には出来ない柔道整復師ならではの技術ですが、現代では必要性が失われてきています(病院が充実してきているので)。
残る後療法に関しては、マッサージ師、整体師、理学療法士と役割の多くが重なっていて柔道整復師ならではの技術というのは存在しません。
特に後療法の代表である「あん摩マッサージ指圧」は柔道整復師が用いることが出来ません(マッサージ師の業務独占により)。
もちろん「マッサージ」という名を使わずに「○○療法」「リラクゼーション」などと称して筋肉をほぐすことは可能です。
可能ですが、ここでは「“柔道整復師でなければいけない何か“が存在するのか?」という話になります。
で、ここまでの流れからは「無い」と考えざるを得ません。
柔道整復師の中には「他資格にはない柔道整復師独自の手技療法が存在する」と反論したい人が存在するかもしれません。
ですが、固定法・整復法のニーズが減り、後療法としての運動療法・物理療法の代替えが病院で可能です。
柔道整復師の存在価値
繰り返しになりますが、「世の中に柔道整復師がいる必要性」というのが昔と比べて希薄になってきているという事です。
これは、時代の流れだけでなく、柔道整復師自身が、自身の価値を薄めてしまっているという現状もあります。
時代とともに柔道整復師の必要性が希薄になる一方で、柔道整復師養成校の乱立により、柔道整復師の数はメチャクチャ増えています。
「接骨院を必要とする少数の人」に対する柔道整復師の数が圧倒的に多すぎるのです。
※なので、離れ島、過疎地などであれば病院の受け皿として機能するはずなのですが、それらに好き好んで出向こうとする柔道整復師は非常に少ないのは致し方ないと思います。
「あん摩マッサージ指圧師」と「柔道整復師」の違い
ここから先は、「あん摩マッサージ指圧師」と「柔道整復師」に関して共通点と違いについて記載していきます。
柔道整復師とマッサージ師の共通点
まず、共通している部分は「独立開業権」がある点です。
接骨院・病院・介護施設などに雇用されても良いのですが、独立開業できるというのはメリットです。
理学療法士は独立開業できません(もし開業したいなら、理学療法士としてではなく、整体師として開業する必要があります)。
ただし、柔道整復師の大きな特徴である「開業権」に関して、「開業の条件(厳密には施術管理者になる条件)」が最近になって大きく変わったのをご存知でしょうか?
でもって、「開業条件の変更」をザックリと要約すると以下になります。
今までは、学校を卒業すれば無条件で開業権が手に入っていたのですが「条件付き」で開業権がもらえるという仕組みになってしまったということです。
この記事では詳しく解説しませんが、興味がある方は以下の記事をどうぞ。
⇒『「柔道整復師=開業できる」は間違い!?制度変更に注意せよ(厚労省へ問い合わせたよ)』
その他、一部のクライアントに対して保険請求できる点は共通です。
※整体師は国家資格でないため、保険請求できません。
また(介護分野で理学療法士の代わりとして)活躍できる点も同じです。
※(理学療法士と比べ、介護報酬は減算されますが)どちらも理学療法士と代替え可能な資格として認められています。
柔道整復師とマッサージ師の違い
前述したように多くの共通点がある「柔道整復師」と「マッサージ師」ですが、違いとしては以下が挙げられます。
- 開業した際の、保険請求できるクライアントの要件が異なる
- 柔道整復師の「整復術」「固定術」を、マッサージ師は有していない
- マッサージ師は“条件を満たしたクライアント”への訪問マッサージが保険適応となる。柔道整復師は訪問サービスは存在しない(整体師のように実費で訪問して、施術することは可能)。
非常にザックリとではありますが、上記がマッサージ師と柔道整復師の違いです。
また、「接骨院における保険適応者が減っていること(厳密には規制が厳しくなっていること)」に加えて、「施設基準を満たすのが大変」「広告規制がある」などの(マッサージ師と同様)のデメリットから「柔道整復師に旨味」を感じることが出来ず、整体師として自費施術院を開業している人も増えています。
マッサージ師も「保険適応者が限られている」「施設基準が存在する」「広告規制が存在する」というのは共通しているため、マッサージ師も「整体院」として開業する人もいたりします。
この点に関しては以下でも述べているので、興味がある方はどうぞ。
ここから先は、「マッサージ師と柔道整復師の共通点」として記載した「介護分野での活躍」にフォーカスを当てつつ、「柔道整復師の悩み」について解説して終わりにします。
介護分野で活躍するのは中途半端
よく、マッサージ師養成校や柔道整復師養成校の就職先に「介護分野」と掲載されているのを見かけます。
ですが「介護分野を生業として働き続けたい」と思うのであれば、理学療法士(あるいは作業療法士・言語聴覚士)になるのをオススメします。
っというのも、理学療法士と「その他の訓練師」では、得られる介護報酬が違います。
そもそも「他の訓練師」も介護分野に進出できるようになった背景には以下があります。
将来開業を夢見てるなら、施設に雇われてはダメ!!
介護分野で働いている柔道整復師の中には以下のように考えている人がいるかもしれません。
ですが、将来開業を目指しているならば介護施設で働くのではなく、接骨院(整骨院)・で働いたほうが将来につながると思います。
なぜなら「介護施設での仕事は、開業条件の一つである“臨床経験”には(一部しか)含まれないから」です。
この点に関しては、以下の記事で「介護施設で働いている柔道整復師さんの声」と一緒に掲載しているので、合わせて観覧してみて下さい。
⇒『「柔道整復師=開業できる」は間違い!?制度変更に注意せよ(厚労省へ問い合わせたよ)』
終わりに
いかがだったでしょうか?
柔道整復師はやりがいのある仕事だと思います。
ですが、(他職種も含めて)役割がオーバーラップしている点が非常に多い。
なので自身の将来性も見据えたうえで、各々のに合った資格を取得し、各々の資格に合ったキャリアデザインを形成していただきたいと思います。
この記事の中に散りばめたリンク先をいかにも掲載しておくので、合わせて観覧していただくと理解が深まると思います。
⇒『「柔道整復師=開業できる」は間違い!?制度変更に注意せよ(厚労省へ問い合わせたよ)』