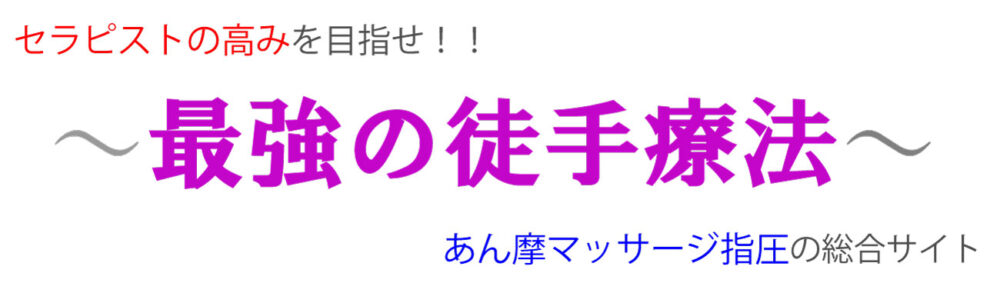この記事では、東洋医学における「生理物質」である精(せい)について解説していく。
精の生理
精とは「生命の根源」と解釈されており以下の2つに分類される。
- 先天の精
- 後天の精
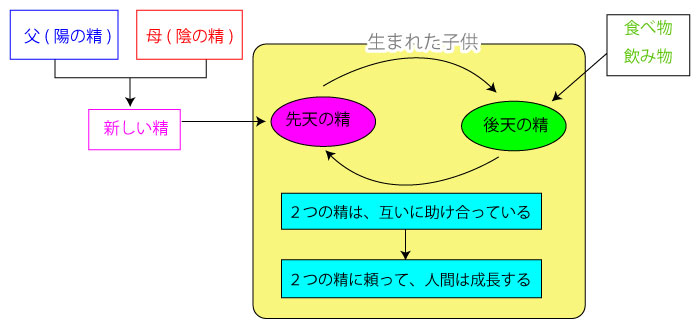
先天の精
先天の精とは以下を指す。
「先天の精」は、出生後、腎にしまわれる。
足りないと、体の発育や知能の発達が遅れたり、寿命が短くなるとされている。
「(後述する)後天の精」により補充される。先天の精が腎の気化作用により気に変化すると原気となる。原気は、腎と臍下丹田に集まって人体の基礎として働く。
関連記事⇒『気(き)って何だ??』
先天の精は、生きていくうえで徐々に減っていく。
したがって、後天の精で補ってあげる必要がある。
後天の精
後天の精とは以下を指す。
「後天の精」は「水穀の精(or 水穀の精微)」と同義である。
「後天の精」は脾胃(ひい)で作られる。
「後天の精」は陰と陽に分けられ、陰分は営気、陽分は衛気になる。
以前の教科書では「営気を水穀の精気」、「衛気を水穀の悍気」と呼んでいた。
営気・衛気の役割は以下の通り。
- 営気⇒津液と合わさって出来る血となり体をめぐる。
- 衛気⇒体を防御する。
後天の精は、生きている限り徐々に減っていく先天の精を補給する。
そのため、飲食物をとらなければ死んでしまうという解釈されている。
「若い人」や「養生をしっかりしている人」は、精が盛んで生命力を含めてすべてが充実しているため、疾病になりにくい。
しかし、老いや過労などにより精が不足すると生命力が弱まり、病にも罹りやすくなる。
精の作用
精の作用は以下の5つ。
- 生殖
- 滋養
- 血への化生
- 気への化生
- 神の維持
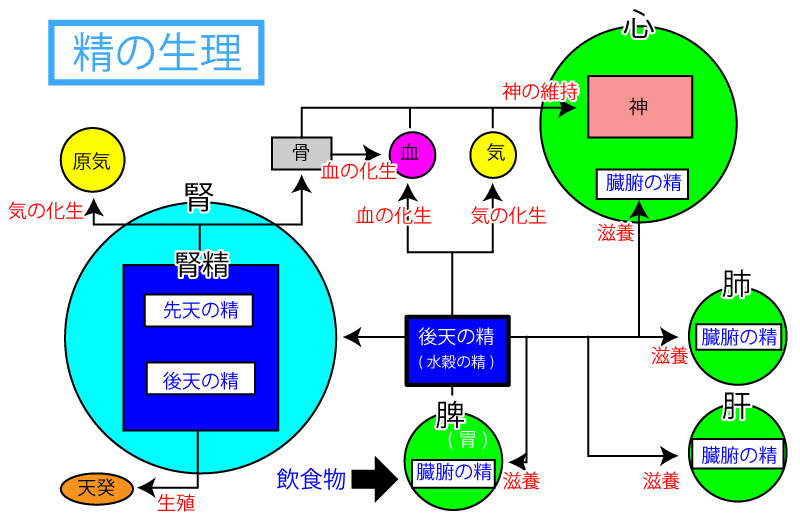
生殖
腎の機能が、ある一定程度まで充足すると天癸(てんき:生殖機能の成熟を促す物質)が産生され、生殖能力が備わる。
※女子では14才・男子では16才。
滋養
組織・器官の生理機能は、精が充足していれば正常に働く。
血への化生
精、特に「後天の精」は血の構成成分となる(=血への化生)。
また、血は臓腑・器官に精を運び、正常な生理作用を発揮させている。
このような「精と血の関係」を精血同源という。
気への化生
精は気にも変化する(=気へ化生)。
精は以下に変化する。
- 先天の精⇒原気に変化
- 後天の精⇒栄気・衛気・宗気
精が不足すると栄気・衛気・宗気も不足する。また、気が不足すると固摂作用の低下により「精」を過度に消耗する。
固摂作用とは:
生理物質を正常な場所にとどめ、やたらに流失するのを防ぐ作用のことである。気は血の脈外への流出、津液の過度な排泄、精の不要な流出を防ぐように働き、その結果、正常な分泌や排泄などが維持される。
神の維持
精が充足すると、神(生命活動の総称・精神活動)がしっかりしている。
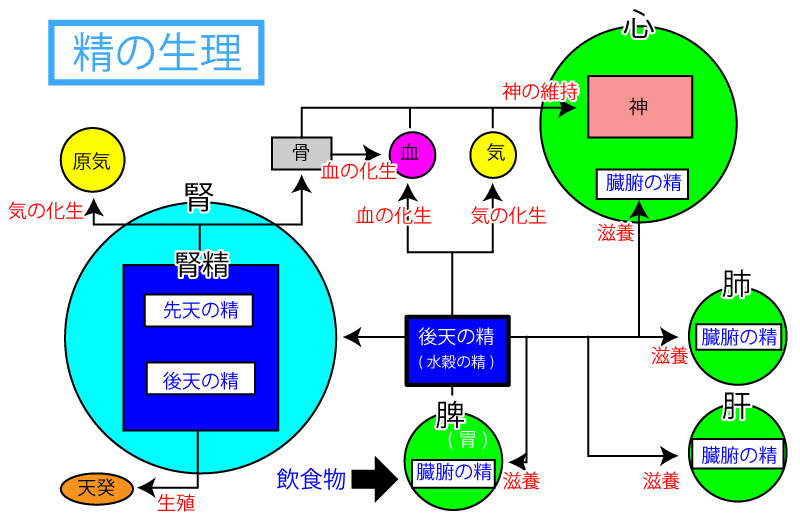
精の病理
精は不足になることで様々な症状が起きる(精が過剰になることは少ない)。
精虚
精虚とは、精が不足した病態のことを指す。
特に精虚は、腎に蓄えられている精が不足するので腎精不足(じんせいぶそく)とも呼ばれる。
原因
精虚の原因は以下の通り。
- 飲食不足⇒「後天の精」が作られない
- 長患(過労・多産堕胎・房事過多)⇒いずれも「先天の精」を消耗する。
その他に、先天の不足、出血、大量の発汗などによる。
症状
精虚による症状は以下などが挙げられる。
- 成長不良⇒先天の精の不足のため生じる。
- 不妊症・陽萎(勃起不全のこと)⇒精は生殖能を主っているため生じる。
- 腰膝酸柔(足腰のだるさ)⇒加齢による「先天の精」の消耗により、骨を満たすことが出来ないため。
- 耳鳴り・難聴・頭髪の脱毛・健忘⇒髄海(脳のこと)を滋養出来ないために生じる。
ほかに、虚弱体質、無力感などの症状が起こる。