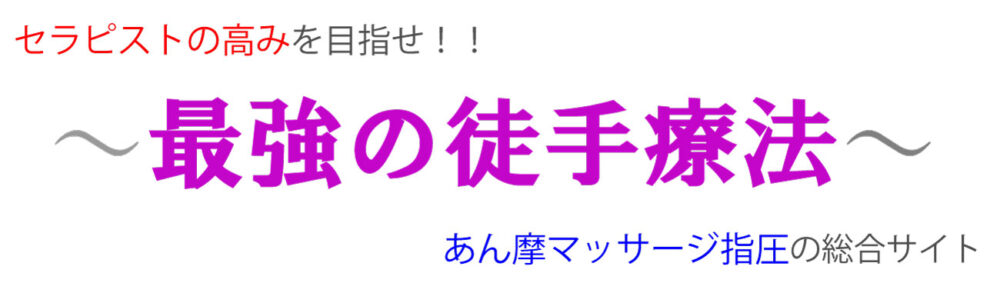この記事では『アプレースクラッチテスト(Apley Scratch Test)』について解説していく。
アプレースクラッチテストの方法・陽性所見・解釈
アプレースクラッチテストの方法・陽性所見・解釈は以下になる。
方法
座位または椅子座位をとらせ、以下の2つの動作を指示する。
動作①:腕を持ち上げ、手を後頭部から反対側の肩甲骨上部を触れるよう指示。
この肢位は「肩関節外転・外旋を組み合わせた可動域」が評価できる。
この肢位をとらせた際の疼痛部位を確認することで有している機能障害・治療手段も類推しておく。
結髪動作と類似するため、主訴が「髪を後ろで結えない・洗髪しにくい」などな症例の評価・治療効果判定に用いることも出来る。
動作②:腕を下げてを背中に回し、反対側の肩甲骨下角に触れるよう指示。
この肢位は「肩関節内転・内旋(+伸展)を組み合わせた可動域」が評価できる。
この肢位をとらせた際の疼痛部位を確認することで有している機能障害・治療手段も類推しておく。
結帯動作と類似するため、主訴が「エプロン紐を後ろで結べない・ズボンを履く際に引き上げにくい」髪を後ろで結えない・洗髪しにくい」などな症例の評価・治療効果判定に用いることも出来る。
かなり可動域が改善してきた場合は「患側だけでなく、健側も評価することで左右差を把握しておく」と、治療効果を追っていく際にも有用となる。
例えば「テストその②」では「患側に比べて、健側の方が4横指ほど上方まで指先が挙げれている」など。
アプレースクラッチテストの動画
ちなみに、上記2つの動作を「左右同時に実施すること」も可動域評価のスクリーニングとして有用である。以下の動画は、左右手で各テストを同時に実施している。
アプレースクラッチテストの肢位がピンとこない方は参考にしてみてほしい。
陽性所見
各動作の可動域制限・疼痛誘発
解釈
肩関節周囲炎(=凍結肩・五十肩など)では、顕著な可動域制限が生じやすいと言われている。
- 複合動作における関節可動域の程度の類推できる。
- 疼痛が誘発される場合は、誘発部位から機能障害を類推できる。
関連記事
以下は肩関節周囲炎についても言及した記事となるので、合わせて観覧すると理解が深まると思う。
⇒『【疾患まとめ】肩関節疾患』
以下の記事では、徒手整形外科的テストの一覧をまとめているので、合わせて観覧してみてほしい。