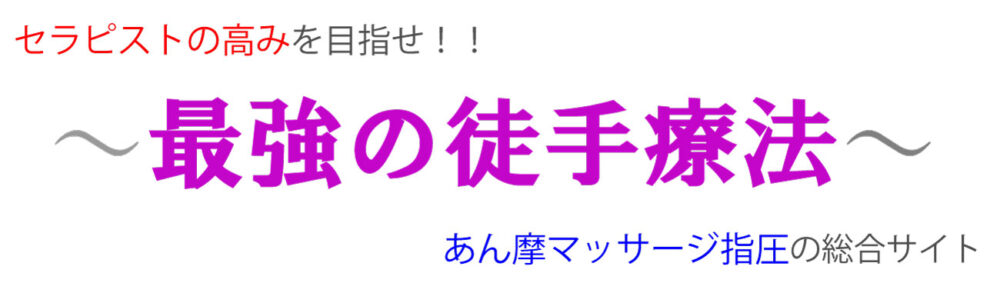昨日、「鍼灸あん摩マッサージ指圧学校の学校説明会」に参加してみました。
理由は以下の通り。
ちなみに、今回は第二弾で、第一弾は以下を参照してください。
学校説明会の内容
今回の学校も、私が住んでいるアパートから電車で30分と、ほどほどな距離。
以下の内容で午前中を使った説明会でした。
- プロジェクタを使っての学校の特徴・試験説明
- 鍼のお試し
- 姿勢に対する授業
学校の特徴
この学校は、「鍼灸・あん摩マッサージ学科」「鍼灸昼間部」「鍼灸夜間部」があり、どれも今年の国家試験合格率100%。
また、この学校は「複数の学校を持っていている法人」が運用していてネットワークが構築できているので、そのグループ内で「国試対策アプリで勉強ができる」や「ネットワーク内での求人のやり取り」がおこなわれていたりするのも特徴のようです。
求人に関しては、このグループ内でしか出回らないクローズな内容にもかかわらず、メチャクチャ求人数が多いのには驚きました。
まぁ、あくまで関東圏における求人の話なので地方出身の私には関係なさそうですが。。
あとは・・「針」「灸」という言葉について以下の説明が。
- 針をイメージしがちだが、実際は鍼。この方が、何となく人に与えるイメージも違うはず。
- 灸は「炙(あぶる)」と書く人がいるけども、違うんですよ。
鍼体験
鍼体験は、各テーブルに鍼が並べられていて、それを「針山?へ刺す」というのを体験しました。
鍼は刺されたことも、刺したこともないのですが、説明も含めた楽しかったです。
鍼は1本1本が滅菌された状態で袋に入って、それを剥がすと「針が入ったプラスチックの筒」が出てきます。
で、その筒からポキっと鍼を外して、「その筒ごと、体表につけて(今回は針山?)、トントン押して刺す」って感じです。
で筒を外して、もう少し深く入れていく。
あとは、隣の人とツボを押しあったりもしました。
ツボの名前は「労宮(ろうきゅう)」で「手指をギュッと握った際に、中指の指先が当たる場所」が目安だそうです。
実際に自分の手で試してみると、確かにツボらしきポイントがある。
色んな効果があるそうですが、その中の一つが「緊張をほぐす効果」だそうで、今度緊張したら使ってみたいと思います。
自分のツボだと簡単に押せましたが、患者さんになると難しいのだろうな。。
自分だったら「何も感じなければ微調整で位置をずらせる」けども、患者さんなら(当たり前ですが)分からない。
鍼ともなれば尚更的確にツボをとらえる必要があるわけで、この技術は「あん摩」や「指圧」でも直接関係しているので親和性のある資格だと改めて感じました。
ちなみに、この学校では、鍼授業の際に、ゴム手袋・指サックをするのも特徴のようです。
感染予防が目的だとか。
どの学校も同様かは分からないのですが、あまりゴム手袋をしているイメージはなかったので「色々な方法があるのだなぁ」と思いました。
そこまで徹底する理由としては「病院・施設での需要なども見越している(それらの場所では、施術院より感染リスクが高いはずだから)」という考えがあるようです。
まとめ
初めて鍼に接したので楽しかったです。
ただ、「鍼の練習するのって大変そうだな」と感じました。
モノを用意しなければいけないので、あん摩マッサージ指圧のように安易に練習でき無さそうだなと。
1本1本密封された鍼を用意し(この学校方式を採用するなら)指サックなんかも必要になるから、練習量を増やすと自然とお金もかかりそうです。。
※ちなみに(割愛しましたが)所々で消毒液も使用します。
「キネシオテーピング指導員資格を取得する過程での勉強」も同じような感想を持ったのですが、その記憶がよみがえってきました。
※まぁ、1本1本で換算すると、そこまで高価なものではないかもですが(値段は分かりません)。
説明会の後に「個別相談がしたい方は残ってほしい」と言われ、かなりの方々が残っていましたが、(以前の説明会のような座談会形式ではなく)マンツーマンな説明会な場合、時間を割いてもらうのが申し訳ないので会場を後にしました。
ただ、学校入り口の掲示板を眺めていると、教員の方が話しかけてくださり小話をしていただくことに。
鍼は非常にザックリと以下に分類されるとのこと。
- 西洋スタイルの鍼
- 中医学の鍼
- 日本から古く伝わっている鍼
この学校では、卒後どのスタイルにでも進めるようなバランスの良い授業を展開しているとのことでした。
関連記事
以下は、「入学直前」「1年生」「2年生」「3年生」における日記・備忘録を記した記事をまとめてある。
入学前の日記
- 無事に退職願を提出! 同封した「感謝の手紙」も公開するよ♪
- 僕の方こそ、感謝です! 先輩セラピストからの手紙内容に感激。。
- 退職まで残り1日 | 多くの別れを経験しました
- 【病院を退職】沢山の「思い出」と「経験」をありがとう!
- 3月:東京生活スタート
1年生の日記
- 1年目4月:学校生活スタート
- 1年目5月:学校生活慣れてきた
- 1年6月:入学後初めてのテスト(前期中間テスト)
- 1年目6月【中間試験】:感想文を書いたよ(テーマは「訪問マッサージの未来について」)
- 1年目6月【資格取得】:理学療法士の試験合格! 先日、認定証が届きました。
- 1年目7月:もう期末試験が始まるよ
- 1年目7月【おススメ書籍】:夜間部の人に「ウエマツ総研」を紹介してみた
- 1年目7月【認定資格】:最新版の「認定理学療法士」の人数が公表された
- 1年目7月【国家試験】:「2020年以降の国家試験の出題構成」が変更になる件
- 1年目8月:夏休みに突入
- 1年目9月:夏休み後半は「新たな挑戦」+「資格取得」を!
- 1年8~9月【ついに始動】:リラクゼーションスキル向上プロジェクト
- 1年目10月:学校後期がスタートしたよ
- 1年目11月:充実した日々が送れてます
- (概要まとめ)筋膜マニピュレーション講習会!6日間を乗り越えて
- 1年目12月:今年最後の試験! そして冬休み!
- 【感想】浪越ファミリー指圧教室へ行ってみた
- 1年目1月:明けまして、おめでとうございます
- 1年目1月【ジョハリの窓】:サロン店長から手紙をもらった
- 1年目2月:無事に進級できました
- 1年目3月:春休み突入!整体学校卒業試験に合格
2年生の日記
- 2年目4月:東京が緊急事態宣言を発令!新学期開始が延期に・・
- 2年目5月:定額給付金10万円+持続化給付金30万円の臨時収入ゲット!
- 2年目6月:店長が辞めた
- 2年目7月:実技テストの結果
- 2年目8月:猿でもわかる「整形外科の授業」
- 2年目9月: 整体(サロン)について語ります
- 2年目10月:第二フェーズへ移行します!
- 【無責任】竹井仁PTの整体院(筋膜博士の筋膜整体院)へ行ったが不在だった件 | 筋膜マニピュレーション/理学療法士
- 2年目11月【新バイト】:整形外科クリニックへの勤務を開始しました
- 2年目11月:気づいたら「ゴートゥーイートの魔術師」になっていた
- 2年目11月:好評にて、訪リハ増回。18時過ぎまで働くことに
- 2年目12月:「コロナ禍における業界話」を先生がしてくれた
- 2年目1月:学校がリモート授業を開始した!実際に体験した感想は・・・
- 2年目2月:「フレイル対策推進マネージャー」のコンテンツを修了したよ
- 2年目3月:最後の実技授業! 先生に指導してもらえて良かった(一生の思い出)
3年生の日記
- 3年目4月:卒業生は各々の道を歩みだす! + 当クリニックは詐欺広告で求人募集している?
- 3年目5月:辞めたい!?「5月病」を予防しよう
- 3年目6月:学校でのパワハラ「資格でも持ってんの?事件」について
- 3年目6月:また整形外科クリニックで理学療法士が辞めた
- 3年目7月:期末テスト終了!そして夏休み!後期カリキュラムも発表
- 3年目8月:夏休みを制する者は国家試験を制する!
- 3年目9月:事業スタート!!!「訪看ステーションの従業員」に対するコンディショニング開始
- 3年目10月:最高難易度だった「卒業試験」
- 3年目11月:卒業試験の結果 + そして退職へのカウントダウン